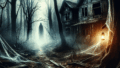ある雨の降りしきる午後、その町の片隅にある古びたアパートの一室に、疲れ切った青年、篠田卓也がいた。彼の目には、深刻な疲労の色が浮かび、薄暗い部屋の中でただ無気力に天井を見つめていた。
篠田は、ここ数週間、不眠に悩まされていた。夜になるとどうにも眠れない。まぶたを閉じるたびに見えてくる奇怪な幻影が、彼の眠りを奪っていた。目を開けても、それら幻影の残像が現実の風景と混じり合い、彼の正気をじわじわと蝕んでいくのだった。
最初にそれに気づいたのは、彼が仕事から帰ってきたある日のことだった。無意識のうちに玄関のドアノブを回した彼の手が、冷たい汗に包まれていたのだ。それは奇妙な感触だった。濡れているわけでもないのに、汗ばんだように、そして何か見えないものが彼の手をじっと握っているかのような錯覚だった。
その頃からだろうか、彼の中で何かが壊れ始めたのは。現実と非現実の境界が曖昧になり、夜毎に彼は夢とも現実とも区別のつかない不安定な幻の世界を彷徨うようになった。そしてそれは、昼をも支配し始めたのだった。
例えば、通勤途中の駅のホーム。人混みの中に浮かぶ見知らぬ人々の表情が、何故か異様に彼を射るように見つめているように思え、息が詰まった。ひとたびその感覚に囚われると、彼は息苦しさに耐えられず、何度も人混みから逃げ出した。
ある日、会社での会議中、彼は突然、ある違和感を抱いた。上司の話がまるで聞こえず、ただ口が開閉するだけに見えてしまうのだ。そして、同僚たちが一斉に彼を見つめ、その視線がまるで肉体を切り裂く鋭利な刃であるかのようだった。耐えられなくなった篠田は、その場で席を立ち、無言で会議室を飛び出した。
彼の頭の中では数え切れないほどの声が渦巻いていた。それらは過去の記憶なのか、未来への警告なのか、それとも単なる幻聴なのかも、今の篠田にはわからなかった。ただ、彼の精神を追い詰める音であることは確かだった。
そんなある晩、彼はとうとう、自らの存在が現実であることを確認するために、自分自身に何をしたのかを確かめることにした。鏡をじっと見つめ、その中に映る自分自身が本当に自分であるのかを確かめた。だが、それは思いもかけない恐怖の始まりだった。
鏡の中の篠田の目は、異なった輝きを放っていた。まるで別人の目で、それが彼自身を冷徹に見下ろしているように思えた。そして、その目が急ににやりと笑った。それは篠田の意志ではなかった。彼は驚愕し、慌てて鏡から目をそらしたが、鏡に映った自らの笑みの残像が消えることはなかった。
その瞬間から、彼はその目から逃げられなくなった。その目はまるで彼の内側からかけられた呪いのように、常に彼を見続け、他人の中にもその目を見つけるようになった。電車の中で向かいに座る乗客や、すれ違う通行人、コンビニの店員の顔の中に、彼の知らないはずのその目と笑みが潜んでいるのだ。
篠田の生活は完全に狂い、次第に家に引きこもるようになった。家の中でも安心できる場所はなく、どこかにその恐怖が潜んでいると彼は感じていた。部屋中に鏡は無数に存在し、そのどれにも彼の知る自分とは違う何かが映るのだ。彼は鏡を見ることができず、また見ないでもその存在を意識せざるを得なかった。
そしてある夜中、ついにそれはやってきた。寝苦しさに耐えかね、彼が布団の中で目を開けると、暗闇の中にぼんやりと、それが立っていたのだ。ゆっくりと浮かび上がる影、その目は真っ直ぐに篠田を見つめ、あの笑顔を浮かべている。その視線を浴びた瞬間、篠田は悟った。それは彼の中にある狂気の化身だった。
声にならぬ叫びを上げ、彼は布団の中から這い出し、無意識に家を飛び出し、夜の街を駆けた。走っても走っても、視線と笑みは消えることなく、彼を追い続けた。街灯の明かりが、まるで彼を照らす舞台装置のように、不安定な影を作り出す。篠田はその影に飲み込まれながら、ただひたすらに走り続けた。
そして、気づけば彼は見知らぬ場所に立っていた。薄暗い公園の片隅、周囲を覆う木々の影が不気味に揺れる中で、篠田は地面に膝をついた。息が荒く、全身が汗で濡れ、頭の中ではあの声がいまだに囁き続けていた。
その時、彼はふと、足元に影を見つけた。自らの影ではない、そう感じつつも彼はそちらに視線を移した。そこにはあの影があり、彼を見つめる目と、変わらぬ笑みを浮かべた口元があった。
篠田の心は限界を超えた。彼は狂ったように笑い始め、その声は静かな夜の中に響く不協和音となって溶け込んでいった。彼の精神はついに、虚ろな幻影の中に飲み込まれてしまったのだ。それが現実なのか妄想なのか、篠田の中でその区別は最早なく、彼自身もまた現実と幻想の狭間に消えていった。
翌朝、公園のベンチには、彼のものと思われる靴だけが残されていた。しかし、彼自身の姿はどこにも見当たらなかった。やがて町から彼の存在も記憶も消え去り、ただあの不思議な目だけが、彼の残した最後の証として、遠くから誰かを見つめ続けているのかもしれない。