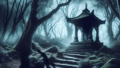僕の名前はタカシ。どこにでもいる平凡なサラリーマンだ。毎日、変わり映えのしない日々を送りながら、それなりに満足していた。そんなある日のこと、僕の平凡な生活に小さな違和感が生じた。
通常、僕は毎朝7時に目覚ましの音で目を覚ます。しかし、その日はなぜか6時30分に目が覚めた。まだ早いなと思いつつ、何だか胸騒ぎがしたのでベッドから出ることにした。普段通り支度をし、食卓に行くと、妻のユミが用意してくれた朝食が待っていた。しかし、どこか様子がおかしい。いつもなら元気よく「おはよう」と言ってくれるユミが、無言でこちらを見つめている。
「おはよう」と僕が声をかけると、ユミはニッコリ微笑んで「おはよう」と返事した。さっきまでの無言の圧力が嘘のようだ。でも微かに胸の奥がざわつく。この違和感は何なのか分からないが、朝の忙しさに紛れて気にしないことにした。
出勤し、いつもの電車に乗る。通勤ラッシュの中、何百という人が密集しているのに、周りの人との距離が異様に近い気がした。混んでいるのは毎日のことなのに、その日は特に圧迫感が強い。しかし、ささいなことだと思い、気にしないように努めた。
会社に着くと、さらに一段階上の違和感が襲ってきた。オフィスの雰囲気がいつもと違う。みんな静かに仕事をしているのに、空気が重かった。僕がデスクに座ると、同僚のカズヤが声をかけてきた。
「タカシ、今日のミーティング、時間早まったんだって知ってた?」
僕は知らなかった。何も聞いていなかったのだ。カズヤの言葉に焦りを覚えつつ、確認のためにメールを見直すが、特に変更のアナウンスはない。僕が何かを聞き逃したのかもしれないが、日頃の感覚からするとおかしい。
そんな些細な出来事が積み重なり、僕の中で不安が膨らんでいく。お昼休み、いつも行く定食屋に向かうと、常連のはずの店員が僕に向かって「いらっしゃいませ、初めてのお客様ですか?」と言った。その言葉にさすがに僕も驚いてしまった。毎週のように通っている店で、顔を覚えられていないどころか、初めてのお客扱いされるなんてあり得ない。違和感が確信に変わる瞬間だったが、それでも僕は何かのミスだと自分に言い聞かせた。
その日、帰宅後にユミにこのことを話すと、彼女はあまり驚かなかった。「そんなこともあるんじゃない?」と軽く流された。ふと、ユミの目を見た時、彼女が誰か別の人のように感じた。その目は、彼女本来の温かさが感じられず、どこか冷ややかで、よそよそしい。
次の日も、そのまた次の日も、同じように些細なズレが続いた。時計が少しずつ狂っていくような感覚。何かがおかしい。それでも、どこで間違っているのか見つけられない。そのまま数日が過ぎ、僕は少しずつ不安を募らせていた。
そして、一週間後、僕はついに決定的な違和感にぶつかることになった。仕事を終え、帰宅すると、何と家のドアが開かないのだ。鍵は確かに持っているのに、全く反応しない。仕方なくインターフォンを鳴らすと、ユミが出てきたが、「どちら様ですか?」と尋ねられた。
僕の頭は真っ白になった。何を言っているのか、理解できなかった。まるで別の世界に入り込んでしまったような錯覚。ユミに事情を話し、ようやくドアを開けてもらった時、彼女の目がまるで僕を完全な他人として見ているかのようだった。
ユミは何もかも知っているのに、まるで僕を知らない人として扱う。この感覚に耐えられなくなり、僕はその場を立ち去った。少し距離を置こうと思ったのだ。
その夜、実家に連絡して事情を説明すると、驚いたことに、母親からも「タカシ、どうしてそんな冗談を言うの?」と言われた。僕は何を言っても伝わらない、何をしても通じないこの感覚に絶望を感じた。
全てがおかしい。この世界が、突然僕のいる場所を拒絶しているかのように。
それから、僕は自分自身の存在が薄れていくような、消えてしまいそうな恐怖に囚われるようになった。もはや何を信じていいのか、自分自身に何が起こっているのか、判断することもできなくなった。
そして、ある日、目を覚ますとすべてが正常に戻っていた。ユミはいつもの通りに「おはよう」と声をかけ、会社でもいつもと変わらない同僚たちが待っていた。だが、僕はその正常さにすら恐怖を感じた。
今でも、あの時何が起こっていたのか分からない。しかし、あの違和感は確かに存在した。何かがこの世の理を狂わせ、僕を別の次元に放り出していたのかもしれない。そして、いつまたその感覚が訪れるのか分からない恐怖が、今も僕の胸に潜んでいる。