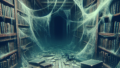これは、ある地方の山奥にひっそりと佇む集落についての話です。この集落は、訪れたことのある者も少なく、外部との関わりを極端に拒む傾向があります。私はある地方紙の記者として、この集落に取材に行くことになりました。情報は限られていましたが、「ムラ」という不気味な習慣があるということで、興味を覚えたのです。
ある日の午後、私は集落を訪れ、村役場で村長を名乗る古参の男、佐藤広樹さんに話を聞くことができました。彼の語りを、ここにそのまま記します。
—
「この村に来るとは珍しいね。まあ、ほとんどの人は帰るわけだが」
佐藤さんはそう言いながら、私にお茶を差し出しました。彼は70代後半と思われるが、彼の目はまるで大昔の出来事を映し出すような澄んだものでした。
「ムラっていうのはね、我々にとっては普通のことさ。外部の人には理解しがたいだろうが、これがずっと続いてきたんだ。昔はもっと大々的にやっていたが、今はほぼ儀式としてだけ残ってるよ」
彼はそう言うと、遠くを見つめるようにして、話を続けた。
「ムラというのは、何代もこの土地で暮らしてきた者だけが参加する儀式のことなんだ。毎年秋になると、村人は山奥の神社に集まり、夜を徹して祈りを捧げる。そして、その祈りが叶うと、村は一年間平穏になると言われている。でも、その代わりに何かを捧げなくてはいけない」
彼の声は次第に低くなり、私は口を挟むことができずに聞き続ける。
「その捧げるものが何かって? それについて具体的に語るものはいない。だけど、知っての通り、村からは時々人がいなくなるんだ。長い年月の間に、何人もの村人がふいと消えてしまった。特に異変が起きた年には、多くの者が姿を消したものさ」
佐藤さんは淡々とした口調で話し続けます。
「わしも若い頃にその儀式に参加したことがある。当時は、よそ者の嫁をもらうのが一般的だった。私の妻もその一人だった。そして、儀式の翌日、彼女は消えた。取り乱したが、誰も何も知らないって口を揃えて言うだけだった。あれから何十年経っただろうな」
彼の表情には複雑な感情が入り混じっているのが見て取れました。
「この習慣が始まった正確な理由は、もはや誰にもわからない。でも、村を守るためには必要なことだと、そう信じてきた者たちがいる。それに従わなければ、どんなことが起きるか…。一度だけ村の誰かが言ったよ。このムラをしなかった年には、ひどい飢饉と病が村を襲ったと」
私はこれを聞いて、はっとしました。それはあまりに現実味を帯びた話だったからです。
「今では、形式的なものになりつつあるが、それでもその夜になると、村人は口を揃えて祈りを捧げる。それがどんな意味を持つかわからなくとも。外の世界からすれば、ただの迷信かもしれないが、ここでは命がけなんだ」
佐藤さんの話は、人間の持つ恐れや信仰がどれほどの力を持つかを改めて考えさせられるものでした。
「外の世界の目には、我々のやっていることは奇妙かもしれない。でも、この山深い村で生きていくための手段なんだ。記者さん、これをどのように伝えるかはあなた次第だが、この村が抱える葛藤も理解してほしい」
彼はそう言って、私を見つめました。その目には、これまで守ってきた伝統への誇りと、そこから逃れられない現実への諦めが同時に浮かんでいるようでした。
佐藤さんの話を聞き終え、私はこの集落の異質で不気味な習慣について深く考えさせられました。文明が発達した現代において、こうした古い習慣がまだ生きていることに驚きつつも、その根底には人間の持つ何か普遍的なものがあるのではないか、と。
帰りの山道を降りる際、背後に控えた集落の静けさが、何とも言えない不気味さを残しました。それはまるで、彼らの信仰が今もなお生き続け、山を支配しているかのような、そんな錯覚を抱かせるものでした。異質さの奥に潜む人間の真実、恐怖と信仰、この集落の話は私の中でしばらく消えることはないでしょう。