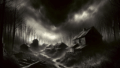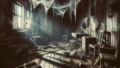夏の終わり、赤とんぼが舞う田舎の村には、長い間語り継がれる奇妙な噂があった。「山の主」と呼ばれる妖怪が、深夜に村を彷徨い歩くというのだ。だが、その詳細を知る者はいない。噂を聞いた者たちは、不吉な出来事を恐れながらも、その姿を見た者は一人としていなかったからである。
村は秋の風が吹き始める頃、一層神秘的な雰囲気を纏う。色とりどりの稲穂が波打ち、月明かりに照らされる夜には、鈴虫の声が響き渡る。その音は薄暗い闇夜を埋め尽くすかのようで、木々の間をかすめる風が、古木たちの囁きを運んでくるのだった。その日も月が高く昇り、村全体に柔らかな銀色の光が降り注いでいた。
村の若者の中に、一人の青年がいた。名は俊夫、幼い頃から好奇心旺盛な性格で、村中の大人たちを困らせるような悪戯をすることで有名であった。彼の両親は早くに他界し、祖母と共に慎ましく暮らしていたが、祖母も最近体調を崩しがちであった。
ある晩、俊夫は夜の山に足を運ぶことを決めた。山の主の正体を突き止め、村を恐怖から解放したいという思いが、彼の胸に湧き上がってきた。彼はこの冒険が村人たちを救う鍵になると考えたのだった。
満月の晩、俊夫はランタンを手に取り、一人で山道を登り始めた。風は冷たく、木々のざわめきは彼の耳に不気味に響いた。それでも彼の足取りは止まらなかった。やがて、山の中腹に差し掛かると、ひときわ大きな古木が彼の前に現れた。その巨木は、何世紀もこの地に根を張っているかのようで、月明かりの下で静かに佇んでいた。
その時、彼の耳に、何とも言えぬ低い唸り声が響いた。心臓が高鳴り、その場に足を止める。そこには、これまで聞いたことのない不協和音が混ざり合っていた。震える手を握りしめながらも俊夫は声のする方に目を凝らし、古木の幹の影に何かの気配を感じ取った。
「誰だ、そこにいるのか?」勇気を振り絞って声を発するも、返事はない。代わりに、木陰の闇がゆっくりと広がり、何かが動き出した。やがて、その影は月光の下へと姿を現した。それは、人のようでありながら、人ではない何かであった。全身を苔で覆われ、瘡蓋のついた皮膚が月光を鈍く反射していた。
その存在は、俊夫をまっすぐに見つめているように思えた。彼はその眼に凍りつくような恐怖を感じ、思わず後ずさった。体が竦み、声も出せず、動くことすら叶わない。山の主は、静かに俊夫の方に歩み寄り、彼の目の前で立ち止まった。
その時、何かが俊夫の心の奥底に響いた。それは昔々、祖母から聞かされた伝説だった。「山の主はこの村を守る存在である。だが、その姿を見た者には恐ろしい災いが降りかかる」と。
俊夫は震える声で言葉を紡いだ。「どうか…どうか、俺を助けてくれ…」
山の主はなおも深い沈黙を守る。しかしその目はどこか哀愁を帯びているようにも見えた。しばしの沈黙の後、その姿が揺らぎ始め、やがて風のように消え去った。
ふと気がつくと、辺りは未明の薄明かりに包まれていた。俊夫はただ立ち尽くし、山の主の去った後に残された静寂を感じ取っていた。それは恐怖と安堵が絡み合う不思議な感覚だった。
村に戻った俊夫は、山の主の存在を語ることはしなかった。誰も彼を信じないだろうし、山の主が村を守る存在であることを知り得た以上、それが最良の選択であると悟った。夜毎に聞こえる鈴虫の音と共に、村の日常は何事もなかったかのように続いていった。
だが、俊夫はあの夜に感じた哀しみを忘れることができなかった。それは人ならざる存在の背負う宿命を垣間見た証であり、人々と妖の境界を超えて存在する、彼の中で静かに息づいている秘密であった。
時が流れ、冬が訪れる頃、村は静かな雪に包まれていた。俊夫は一人、再び山道を歩いていた。祖母は静かに永い眠りにつき、今は彼だけがその秘密を知る者としてここにいる。山の主が再び姿を現すことはなかった。だが、彼の胸に残されたその記憶は、村を訪れる微かな風のように、いつまでも消え去ることはなかったのである。