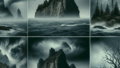私はある地方の小さな村でその家を目にした。村を包む静けさは、都会の喧騒とは異質のもので、時折鳥のさえずりが遠くで響く以外は、まるで時間そのものが停滞しているかのようだった。夕暮れ時、風に乗って漂う草いきれの匂いが過ぎ去る夏を惜しむかのように鼻先をかすめ、私はその魅力に引かれるように村を訪れたのだ。
その村には古びた伝説があった。「屋根裏の女」という、誰もが知っているが語り継ぐことを避ける奇怪な話であった。村人たちはその家に近づくことを禁じ、子供たちは決して立ち入らぬように言い含められていたという。しかし、旅人である私はその噂を確かめたいという欲求を抑えることができず、探し求めて村を彷徨った。
家はすぐに見つかった。村はずれにぽつんと立つその家は、どこか憂いを帯びた佇まいで、まるで深い悲哀を語っているようだった。屋根には苔が生い茂り、朽ち果てた窓枠は奇妙な陰影を落としていた。私は、何かに取り憑かれたように足を進め、玄関の扉を押した。風に朽ちてかすかに揺れる木製の扉が、かすかな軋みを上げ、私をその内部へと迎え入れた。
家の内部はひんやりと薄暗く、壁一面には年代を感じさせる古い壁紙が剥がれ落ちている。天井からは、埃をかぶったシャンデリアが糸を引いたように垂れ下がっており、その下にはいくつかの家具が埃に覆われてぽつぽつと並んでいた。廊下を進むに連れ、年月が凝縮されたような空気が私を包み込み、不安がじわじわと心の底から湧き上がるのを感じた。
階段を上り、屋根裏へと続くドアの前で足を止めた。ドアはかつての白塗りが無惨に剥げ落ち、ただの木の板のように無機質である。一瞬、引き返すべきかと迷ったが、しかしその答えを出す間もなく、何かに引かれたようにドアノブに手をかけた。
ぎいっと、耳障りな音を立ててドアが開く。乾いた埃のにおいが一気に押し寄せ、私は思わず顔をしかめた。薄暗い屋根裏にはいくつかの木箱が無造作に置かれ、蜘蛛の巣が辺り一面を覆い隠していた。そして、部屋の奥に目を凝らすと、そこに人影らしきものが見えた。動かないそれは、どういうわけか私を引き寄せた。
その人影の前に立つと、それが女の置物であることに気づいた。身を縮こまらせるように佇むその姿は、まるで何かを訴えかけるかのようだった。私は震える手でその像に触れようとした瞬間、不意に背後から風が吹き抜け、かすかな声を耳にした。それは誰かが囁くような声で、何を言っているのかは聞き取れなかった。しかし、その声が私の心の中で何かを揺さぶり、得体の知れない恐怖心が背筋を駆け巡る。
慌てて振り返ったが、そこには誰もいなかった。ただ一つ、ふいに冷たい視線を感じた私は、もう一度背後を振り返った。木目の模様が壁一面に打ち寄せる波のように浮かび、その奥にまるで沈んでいくように、彼女の瞳が揺らめいた。置物の瞳は、屋根裏部屋の薄暗がりの中で不自然に輝き、その冷たさを一際増して私を睨みつけているようだった。
恐る恐る視線を逸らせないまま、一歩後ずさる。すると何かにつまずき、私は転倒する。そしてその衝撃で、屋根裏の床からは何か小さな物がコロリと転がり出た。それは古びた日記帳だった。
表紙に掻き殴られた文字と揃っていないページの厚みは、持ち主の心の乱れを無言で物語っているようだった。恐怖と好奇心に駆られながらも、その日記帳を手に取ると、私は中を開いた。
日記は、かつてこの家に住んでいた女性の日々を綴っていた。最初の数ページは、穏やかで幸福そうな家庭の様子が描かれていたが、次第に不穏な内容へと変わっていく。夫の奇妙な行動、見知らぬ人の訪問、そして夜毎に聞こえるはずもない声。日記を読み進めるにつれ、その恐怖と悲しみが女性の心を蝕んでいく様がありありと脳裏に浮かんだ。
最後のページには、震えた手で書かれた断片的な言葉が並んでいた。「もう限界」「逃げられない」「私を屋根裏に」――そこには、彼女が絶望の果てに見た光景が散文的な走り書きで示されていた。
私はそのページを見つめ、思わず後退する。まるで彼女自身が、この屋根裏で何かに取り憑かれたかのように、私の意識をつかんで離さなかった。逃げるべきだという心の叫びを無視できず、私はどうにかしてその場を後にしようと決心した。そのとき、足元が急に不安定になり、私は尻餅をついてしまった。
ふと顔を上げると、置物の視線が今までにも増して冷たかった。恐怖のあまり動けずにいる私に、彼女の声が無言で囁く。「私の代わりに」と。その瞬間、私は背筋を氷のような寒気が走るのを感じた。立ち上がり、ふらつく足で必死に階段を駆け下りた。
ようやく家から外に出ると、冷たい風が私を迎え、息苦しさから解放された。しかし、その後ろで、確かに何かが囁いていた。あの家にはまだ何かが蠢いている――そんな予感を感じながら、私は村を後にせざるを得なかった。屋根裏部屋の静寂は、今もなお旅人たちによって破られ続けるのかもしれない。
あの村の者たちが決してその家に近づかない理由が、今ではわかる気がした。恐怖に満ちた記憶は、それ自体が生き続け、訪れる者を永遠に呪縛するのだ。私は再びその村を訪れることは二度とないだろう。けれども、胸の奥底には、決して拭い去ることのできない不安が、今もなお静かに棲みついている。