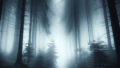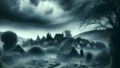薄暗い地下室に張り詰める空気は、冷たく湿った静寂によって硬直していた。この場所は、かつて賢明な科学者たちが会議を行い、革新的な発明を成し遂げたはずのラボだった。だが今や、誤った天才の実験場と化し、倫理という言葉すら忘れるほどに、長く深い夜の底に沈んでいた。
この場所に足を踏み入れる者は、もう名前が消え去ってしまった一人の科学者、薫だった。彼は考究心を抱え、かつては称賛を浴びることを夢見ていた。だがその夢はいつからか悪夢へと変わり、そして最後の一線を越えてしまったのだ。
地下室のほうれん草色のランプが淡い光を放ち、影を刻々と変化させる。彼の目の前には長方形の金属台、その上に横たわるものはかつてそうであった、人間の姿を辛うじて保っているだけの、異様な姿である。彼は「成功作」と呼ぶことに決めた、その存在を見つめた。だが、それは成功とは程遠い乱雑なパズルのようなものだった。皮膚はまだら模様に瘴気のごとく変色し、無残にも歪んだ関節が骨の軋む音を奏でる。
薫の頭には、その失った日々の記憶が蘇る。彼はつい数年前、この偽りの知識の芸術に没頭し始めた。それは生命の本質に迫るという名目で、秘密裏に始めた人体実験の連鎖だった。彼の理想は、神が創り得なかった究極の存在を人間の手で造り上げることだった。だが、造り上げたそれは、まるで自らの罪を体現したかのようで、毎晩の囁きによって精神を蝕まれる。
「薫……助けてくれ……」呻くようなか細い声は、一度としてその目を覚ますことのなかった被験者たちの幻影で、彼の耳に澱のようにこびりついて離れない。彼は、自らの創造物に安堵どころか、耐えがたい恐怖を覚えていた。それは、彼を永遠に苦しめる生ける悪夢のようであった。
人体実験が始まった初期、薫はいくつかの臨界実験を重ね、ついに思考をもつ生命体を実現しようと試みていた。それは、生命そのものの神秘を手中に収めることであり、彼は興奮に身を震わせていた。だが、次第にその熱狂は次第に冷えかけ、限られた知識と倫理の境界が溶け始めた。仲間たちは一人また一人と離れてゆき、遂には薫一人を残すのみとなる。
ある夜、薫は自身の失敗を糊塗するかのように、最新の試薬を被験体に注入した。彼の意識がぼやけ、朝日に照らされて見上げた天井は、蜘蛛の巣が絡むように歪んで見えた。気がつくと、周囲の静寂は消え失せ、代わりに不気味なざわめきが耳を打った。機械音のような、彼岸の世界からの呼び声にも似て、反響する。
「こんなはずじゃ……」自分に言い聞かせるように呟くが、その声は虚しく地下室の奥へと溶け込んでいく。露見した身体の変化は、とうに想定の範囲を越えていた。細胞が異常に増殖し、自身の体そのものが意志をもって蠢いているかのようだった。身体の外縁は、切れ目なく繋がり、溶け合っていく。なぜだか、彼はそれに対して全くの抵抗も感じない。
この世のものとも思えない、生々しい音が部屋を満たした。薫の体の中で、自身とは異なる存在が目覚めようとしている。彼の瞳には、かつて見慣れた景色が、人体と呼ばれるべき姿を失い、悪夢の一部となる瞬間が映し出されていた。
いつの間にか、彼は理解し始める。この狂気の中で根底の理が崩れ去ることを。それは、結局のところ文明の産物としての彼の誇示であり、そして何よりも拭い去れぬ絶望という名の影だった。
やがて彼は、自身の額を見る。そこには、刻まれたような赤い痣が浮かんでいる。それは肉体の変容が自らを生み出すことを示す、おそらく避けがたい証。他の誰の手でもなく、自分自身の手で施された細胞生成のしるし。
このまま夜が深く沈んでいけば、薫はもはやかつての自分ではいられないだろう。そして、彼がこの世に新たに残すことができるものは、ただ一つ、償いようのない後悔であった。
時間の輪が逆巻き、暗闇に彼の声が吸い込まれていく。「何故……こんなことに」と、悲痛な叫びが自分の中で常に鳴り響く。しかし、その問いに答えられる者は、彼自身もまた存在しなかった。
薫は意識を絶たれるようにその場に崩れ落ち、その身からは凍りつくような静寂が立ち上がっていった。地下室の深き闇の中で、生命の営みが言い尽くすことのない苦悶の声をもって続いた。それは彼が捨て去ってしまった生命倫理への途絶えた道しるべ、そしてもはや戻ることのできない失墜の結末だった。