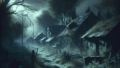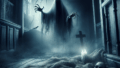数年前、僕は静かな山間の村である不思議な体験をした。その村はどことなく時間が止まったかのような場所で、古い伝統が今も強く息づいているように感じられるところだった。都会の喧騒に疲れ、のんびりとした時間を過ごしたいと思って、山登りが趣味の僕は、インターネットで見つけたその村を訪れることにした。
村に着いたのは、秋も深まった涼しい午後だった。すぐに宿を探し、村の中心にある小さな民宿に泊まることにした。民宿の女将は親切な人で、村の歴史や伝説について色々と話してくれた。しかし、彼女がとくに強調したのは「夜には外を歩かないように」という一言だった。不用意に出歩くと、「見てはいけないものを見てしまう」ことがあるのだという。
その言葉がずっと頭の片隅に引っかかりながらも、僕は好奇心を抑えきれず、翌日も村を見て回った。古びた神社や人懐っこい村人たちとの会話、全てが新鮮で、都会では味わえない心地よさを感じていた。
しかし、その夜、民宿で晩ご飯を済ませ、部屋に戻った僕は外から聞こえてくる不思議な音に気がついた。鈴の音のような、しかしどことなく悲しげな響きのする音だった。不思議に思った僕はカーテンをそっと開け、夜の闇に目を凝らした。
月明かりは微かに村を照らしていたが、どこかに鈴を鳴らしている人の姿はない。代わりに、少し離れた木々の間を何かが移動する影を見たような気がした。
その瞬間、僕は背筋に冷たいものを感じた。まるでその影がこちらを見ているかのような、奇妙な感覚にとらわれた。女将の「見てはいけないものを見てしまう」という言葉が頭をよぎり、僕は急いで窓を閉め、カーテンを引き、布団に潜り込んだ。
しかし、どうしても眠ることができず、あの音が耳から離れなかった。次の日、旅行を切り上げる決心をし、女将にお礼を言ってから帰る支度を始めた。民宿を出るとき、女将は何かを言いたげだったが、結局何も言わなかった。
都会に戻った僕は、あの音や影のことを忘れたわけではなかった。むしろ、日常が戻るとその不可解な体験はますます頭に残り続けた。インターネットで村とその周辺のことを調べるうちに、その地域にまつわる不気味な伝説を知ることになった。
その村には「夜鳴きの鬼」と呼ばれる妖怪が古くから伝えられているという話だった。普段は人目につかないように隠れているが、夜になると鈴の音を鳴らしながら村をうろつくとされている。そして、好奇心で夜の村を歩く者を影の中から見つけ、心を囚われさせるという。
そうして一度でも心を囚われた者は、日常に戻ってもその音を思い出し、やがて再び村に呼び戻されるというのだ。最終的には、その者も夜鳴きの鬼と共に闇に溶け込んでしまうのだという…。
その話を知ったとき、理解した。僕があの夜に感じた恐怖は、ただの気の迷いなどではなく、本当に「見てはいけないもの」だったのだ。しかし、僕は都市に戻ってからも何度かふとした瞬間にあの鈴の音を耳にするようになっていた。
最初は疲れやストレスのせいだと思っていたが、回数が増えるにつれ、これはあの村の影が僕の後を追ってきているのではないかと疑うようになった。
それから数ヶ月が経ち、僕は気付けば再びあの村を訪れる計画を立てていた。そしてそれが、自分の意思であるのか、「夜鳴きの鬼」に導かれているのか、僕には判断がつかなくなっていた。
友人たちには「仕事のため」と言って出かけることにし、数日後には再びあの村に着いていた。変わることのない静けさと、どことなく懐かしい雰囲気に包まれた村に足を踏み入れたとき、僕はまるで家に帰ってきたかのような奇妙な安堵感を覚えた。
あの民宿に泊まり、再び女将の笑顔に迎えられた。そしてその夜、僕は待ちわびたようにカーテンを少し開け、鈴の音がどこから聞こえてくるのかを窓辺に立って待っていた。
そして影は現れた。今度はその姿がはっきりと見えた。古びた着物をまといながらも異様に長い髪の女性の姿。しかしその顔は、夜の闇に溶け込んで見えない。鈴を持った手だけが月明かりに照らされて、白く細い指が鈴を揺らした。
僕はその鈴の音に吸い寄せられるようにして窓を開け、そっと声をかけた。「そこにいるのは誰だ?」と。
その瞬間、影の目が輝きを放ち、細い声でこう答えた。「私を見たあなたは、もうここを離れることはできません」
驚きと恐怖で僕は振り返ろうとしたが、身体は動かなかった。それでも心のどこかで、それが避けられない結末であることを理解していた。僕は静かに、しかし確かに、その影の方へと一歩を踏み出した。それからの記憶は薄れていくばかりで、どこにどう行ったのかも思い出せない。
ただ一つ、気づいたことがある。それはこの体験を引きずりながらも、今の僕は以前より少しだけ夜が待ち遠しくなったということだ。毎晩、窓の外で聞こえるあの鈴の音を待ちながら、僕はそれが心地よくもあるということに気づいたのだ。まるでその音が、今では僕にとっての新しい日常であるかのように。