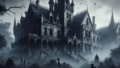ゆったりとした午後の日差しが窓から差し込む居間で、葉子は何気なく新聞をめくっていた。風鈴が涼やかに揺れる音が耳に心地よい。そんな穏やかな日常のひとこまだった。窓の向こうには静かな田園風景が広がり、遠くには山並みが薄く霞んで見える。
ある日、葉子は一枚の写真を見つけた。古ぼけたアルバムの中に挟まれていたそれは、家族旅行で訪れた海辺での一枚だった。砂浜に立つ彼女と弟の晴也、そして、そこにはいないはずの白いドレスの子供が写っていた。どうしてだろう。思い返してもその時、一緒にいた記憶はない。葉子は不思議に思い、アルバムを閉じたが、一度芽生えた不審の種は心の底に残った。
数日後、葉子が台所で夕食の支度をしていると、背後でかすかな足音が聞こえた。彼女は振り返ったが、そこには誰もいない。家にはまだ誰も帰っていない時間のはずだった。風のせいかもしれないと自分に言い聞かせ、葉子は再び料理に集中しようとしたが、どうにもその音が頭から離れない。
翌朝、居間で紅茶を飲んでいると、またもや奇妙なことが起こった。カップの縁がふと揺れ、何の前触れもなくテーブルに沈んでしまったのだ。葉子は驚きつつも、それがただの錯覚であればいいと願った。だが、日を追うごとに、彼女の心は次第に不安に飲まれていった。
ある夜、家族が寝静まった頃、突然耳元で誰かが囁く声を聞いたような感覚に襲われた。「おかえりなさい」という声が、暗闇の中から聞こえたような気がした。葉子ははっと目を開け、部屋を見回したが、当然誰もいない。疲れているのかもしれないと再び寝ようとしたが、さらに強く感じる孤独と不気味さに襲われ、寝付けない夜を過ごした。
翌週、葉子の心に根付いた不安は更に現実味を帯びたものになった。いつも通るはずの近道が、突然見知らぬ場所に繋がっていたのだ。馴染みのある枝が映る通り道を抜けると、見覚えのない古びた祠がぽつんと佇んでいた。その祠からは奇妙な気配が漂い、葉子は背筋を凍らせながら急いで先を急いだ。
日常は少しずつねじれていき、リアルと幻想の境界が不明瞭になっていく。葉子はその違和感を感じながらも何もできない無力感に苛まれていた。家庭や仕事、友人関係、どれもが普段通りに機能しているようで、その裏側にどこか異質な何かが潜んでいるように感じられた。
その翌日、通勤中に窓の外を眺めていると、そこに見慣れた風景が広がっているはずだった。しかし、何かが違っていた。電線に止まっている鳥の数が奇妙なほど均等で、そして同じ位置でくるりと一斉に方向を変える。思わず目をこすったが、夢ではないことを確認して、葉子は背後に不安の影を感じた。
家族に相談したくとも、言葉にすることはかなわず、原因もわからないその感覚に一人取り残された。日々の暮らしはそのまま続いていくが、壊れかけた現実に葉子はどう対処することもできなかった。やがて彼女の中で何かが静かに崩れていくのを感じながら、日常という名の檻に閉じ込められたまま、抜け出す術を知らぬまま、葉子はただ、流れる時間に身を委ねるしかなかった。
その夜、葉子は夢を見た。白いドレスの子供が、海辺で優しく微笑んでいる。それは思い出の写真と同じ光景だったが、一つだけ違っていた。子供の後ろには、ぼんやりとした人影が見え、その輪郭は徐々に葉子の方へと歩を進めて来る。影はゆっくりと、手を伸ばし、葉子の頬に触れた。冷たい指先が触れた瞬間、目の前の世界がぐにゃりと歪んで消え去った。
目が覚めたとき、彼女は深く息を吸った。部屋の中は静まり返っており、いつもと変わらぬ朝が来ていた。しかし、葉子の心の奥底には、再びあの影が現れるのではないかという恐れが渦巻いていた。そんな彼女の脳裏には、母親が幼い頃によく話してくれた言葉が浮かんでいた。「魂は、想いのいく先を知るものだから」。葉子は密かに、日常の枠から解き放たれる日を待ち望みつつ、その日を迎える準備だけはしっかりとしようと決心した。
こうして、壊れかけた日常の中で、葉子はただ存在し続けた。現実と幻想の境界の狭間で生きる彼女に、ふとした瞬間に訪れる異変は、これからも度々彼女を包んでいくのだろう。それでも彼女は、壊れていく日常の中で何かを見つけることができるのを、どこかで待ち続けていた。人は皆、それぞれの形で日常の崩壊を経験する。ただ、その崩壊の先に何が待っているのかを知るのは、叶わぬ望みかもしれない。葉子は静かに微笑んで、再び窓の外を眺めた。