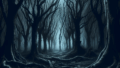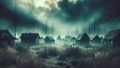夜の静けさに包まれたその古びた館は、村を見下ろすように山の中腹に佇んでいた。誰も住むものはいないはずのその建物は、かつての豪華さを窺わせる装飾をなお残し、その姿は明らかに時を止めていた。村人たちは、その館に近づくことを避け、恐れの混じった囁き声でその名を語った。「呪われた館」と。
ある晩、好奇心に満ちた青年、田中直樹は、村の伝説を確かめるべく、その館を訪れることを思い立った。夜更けの冷たい風が彼の背中を押し、枯葉がカサカサと音をたて足元を覆う。月明かりはかすかに彼の道を照らし、不気味な影を木々に落とす。館に近づくにつれ、高鳴る心臓の鼓動は、静まり返った夜の中で一層大きく響いていた。
田中が木製の重い扉を押し開けると、錆びた蝶番が甲高い泣き声を上げた。中に入った彼の鼻を突くのは、カビと湿気が混じり合った重い空気であった。広いホールは暗闇に包まれ、月光のみがかすかに床に幾つかの光の斑点を落としている。
壁を這うように歩き出した田中の目に最初に飛び込んできたのは、巨大な肖像画だった。それはかつてこの館に住んでいた貴婦人の姿を描いたもので、その瞳はどこか遠くをじっと見つめているようだった。田中はその目がまるで、彼の心の奥底を見通すかのように感じ、不意に視線を逸らした。
彼は階段を上り、ひとつずつ部屋を探索することに決めた。廊下の暗闇に足音がこだまするたびに、背中に冷たい汗が流れる。幽かな風の音に混じって、何かが囁くような音が彼の耳に届く。時折、壁の向こうからは家具が軋む音や、何かが這い回るような音さえ聞こえてきた。恐怖と好奇心がない交ぜになり、不安でありながらも進むことをやめられなかった。
屋敷の最上階にたどり着いた時、田中は一際大きな扉に目を留めた。他の部屋とは一線を画す壮大さを感じさせるその扉の向こうに、何か特別な秘密が隠されているように思えた。勇気を振り絞り扉を開けた彼は、そこで驚くべき光景を目の当たりにする。
この部屋には、異常とも言える静寂が満ちていた。中央には、円形のテーブルとその上に広げられた古びた地図。地図には、数々の秘儀と呼ばれる暗号が無数に記されていた。壁には何体もの古めかしい鏡が掛けられ、その全てが田中自身の姿を映し出しているように見える。しかし、それらの鏡の中で一つだけ、彼ではない何者かの姿が、微かに歪みの中からこちらを見つめていた。
その瞬間、彼は背筋に何か恐ろしいものが這い回る感覚を覚える。鏡に映る影の中の人物は、確かにこちらに微笑みかけている。それは、田中の一族に伝わる失われた祖先の姿のようにも見えた。驚愕した彼は鏡に飛び込んで、その影の正体を暴きたくなる衝動に駆られた。
だが、一歩を踏み出したその時、背後から冷たい手が彼の肩を掴んだ。振り返った彼の目に映ったのは、肖像画の貴婦人の姿。その眼は深遠なる虚無をたたえ、彼を底知れぬ恐怖の淵へと誘うかのようであった。瞬間、彼の意識は断ち切られた。
翌朝、村人たちの通報により、館を訪れた捜索隊が彼を発見したのは、あの不気味な古びた部屋だった。床に横たわる田中の顔は、恐怖と驚愕に歪んだままであった。その表情に宿る一片の静けさは、それでもどこか安堵の色を含んでいた。
田中は奇妙にも眠るようにそのまま還らぬ人となったが、村人たちは再びその館を訪れることを拒み続けた。ただ彼の遺した小さな手帳には、最後に彼が見たであろうあの影の笑顔の素描が、震える手で描かれていたという。村の伝説はまた新たな物語を残し、静かに時の流れに溶け込んでいった。