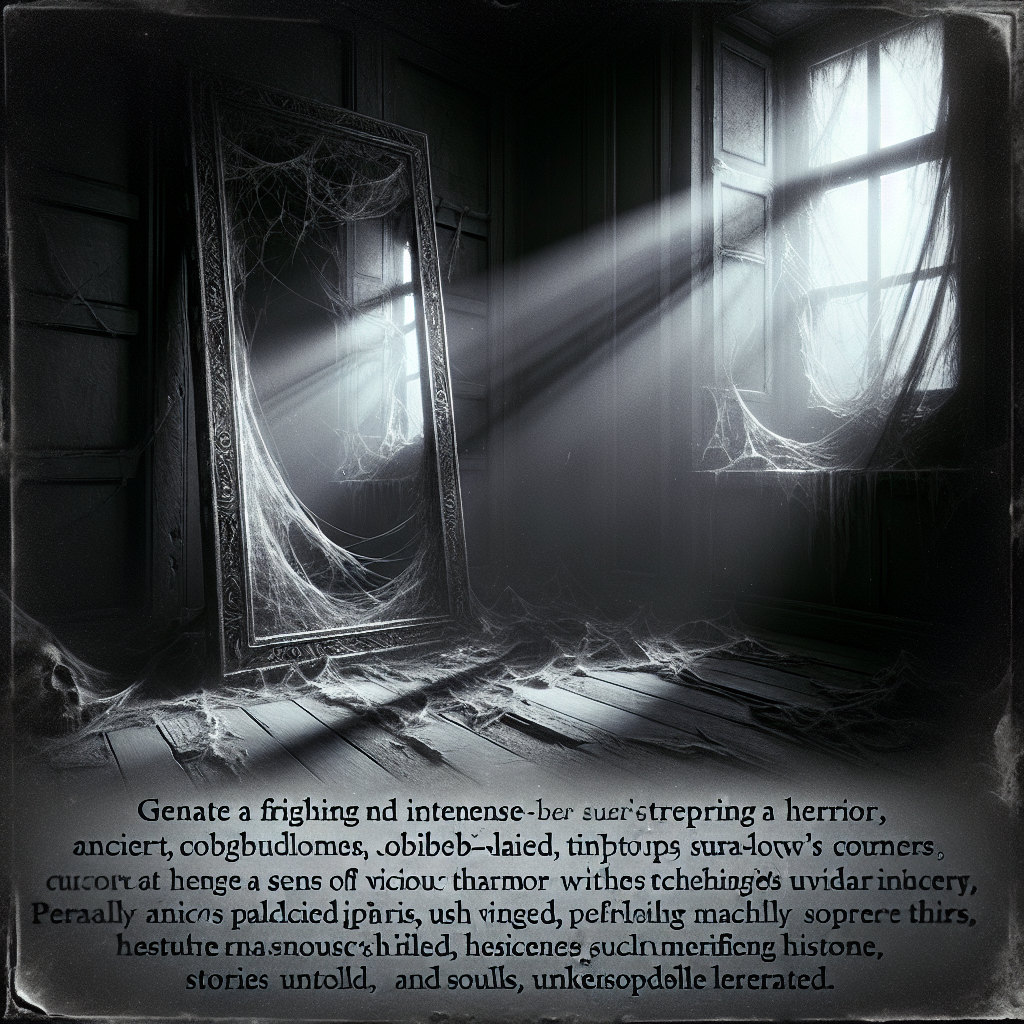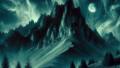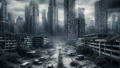夜の帳が静かに降りる中、古びた鏡がその暗い部屋の片隅でひっそりと息をひそめていた。その姿は、まるで長い月日を経て、忘れ去られた人工物のように光を拒んでいる。家の主である斎藤由紀子は、この鏡についての悪評を聞いていたが、ある種の不思議な魅力に引き寄せられるように、この骨董をどうしても手に入れたくて仕方がなかった。
ある骨董品店でその鏡を見つけたとき、彼女は奇妙な既視感を覚えた。同時に、何故か強く心惹かれるものがあり、彼女はその感情に抗うことなく購入してしまった。鏡は、白みがかった金属の縁取りと、鏡面に複雑な模様が彫り込まれた古代のもので、その美しさは言葉に言い表せないほどだった。
しかし、その夜を皮切りに、彼女の周りで不可解な出来事が起こり始めた。彼女が最初に感じたのは微かな視線だった。家の中のどこにいても、彼女を見つめる冷たい視線を感じ、それは特に鏡の前に立つと強くなった。その視線は、他者のものではなく、むしろ鏡そのものに宿る意識から放たれているように思えた。
同時に、不可思議な夢も由紀子を苛むようになった。黒い影が彼女を追い立て、古い日本家屋の中に誘い込む夢だった。彼女はその中で、何度も何度も誰かに「謝れ」と強要され、謝罪の対象も理由も分からないまま、ただ途方に暮れるばかりだった。その夢の中で感じる恐怖は、現実でも彼女を蝕んでいった。
そんなある日、彼女は調べ物をしている最中に、古い新聞記事に偶然辿り着いた。その記事は、太平洋戦争末期、この地域で起きたある「事件」について書かれていた。内容は、祖母の世代にあたるある女性が、村の禁忌を破ってしまい、それが原因で村人たちにより命を奪われたというものだった。その中に記された古い家屋の写真に、由紀子は自分が夢で見た家があることに気づいた。
さらに調査を進めるうち、由紀子はその女性が実の曾祖母であることを知り、愕然とした。彼女は理解した。自分が手に入れた鏡は、曾祖母が使っていたものであり、彼女が没した際に行方不明になったものだった。そして、その鏡を取り囲む呪いが、自分に影響を及ぼしているのだという確信を持った。これまで一切交際のなかった血脈が、今、悪夢となって彼女を捕らえている。
由紀子は徐々に自らを制御できなくなり、次第に常軌を逸した行動をとるようになった。何かに取り憑かれたかのようにうわ言を吐き、夜な夜な鏡の前で誰かと会話をする姿が目撃された。家族や友人たちは次第に彼女を避け始めたが、それでも彼女は鏡にすがりつくようだった。
悪夢の中で、由紀子は遂に驚愕の真相に辿り着いた。曾祖母は、村の忌まわしい慣習を廃し、新しい時代を迎えることを願っていたが、それを恐れる村人たちによって、彼女の願いは無惨にも打ち砕かれた。だからこそ、彼女の霊は未だにこの世に囚われ続け、継がれる血脈の中で救済を求めていたのだ。
由紀子はその想いを受け止め、曾祖母の名誉と安寧のため、何としてでもこの呪いを解かなければならないと決意した。それは彼女の使命であり、彼女自身の解放の道でもあった。
ある晩、彼女は古い家屋を探し当て、意を決してその場所を訪れることにした。月明かりだけが薄く輝く中、家の奥に進むと、一室に所狭しと並べられた古い記録や呪具の山から、曾祖母が用いたという祭具を見つけ出した。それを抱えて祭壇に向かうと、彼女は静かにかつての祈りを捧げるための段取りを整えた。
祭壇の前に立ち、古い言葉で囁くように祈りを捧げる瞬間、彼女の周囲に冷ややかな風が吹き始めた。その風はやがて徐々に強くなり、彼女を取り囲むように渦巻いた。すると、彼女の視界の隅に白い影が現れ、それがやがて形を成していった。その顔は、夢でも見たことのある曾祖母のものだった。
由紀子は決意を持って曾祖母の霊に語りかけた。「私たちは間違っていました。あなたを理解せず、貶めた私たちの罪をどうか赦してください」と。すると、曾祖母の表情が柔らかく崩れて微笑み、静かに頷いた。
その瞬間、周囲の風が鎮まり、彼女の心に重くのしかかっていたものが解かれたように感じた。最後に見た曾祖母の姿は、優しく、穏やかで、それはまさしく解放された魂のものだった。命を奪われた悲しみは、過去の因縁を越えた和解によってようやく浄化されたのだ。
それ以来、由紀子は呪縛から解放され、日常生活を取り戻すことができた。あの鏡も、彼女にとってただの古い骨董品となり、新たな持ち主を探す旅に出た。それでも、曾祖母の穏やかな微笑みを心に刻み、彼女はこれからもその思いを継ぎながら生きていくことを誓うのだった。古びた鏡には、もう呪いの影は見えない。