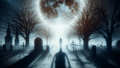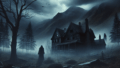むかしむかし、小さな村にトシオという少年が住んでいました。トシオは村の中ではおしゃべりが苦手で、いつも絵本を持ち歩いていました。本の中に描かれた不思議な世界と動物たちが、彼の唯一の友だちでした。
ある日のこと、トシオは村外れの森にひとりで探検に出かけました。その森は村の人たちが「呪いの森」と呼び、誰も近づこうとしませんでした。大人たちは「村を血で染める呪いの木がある」と言い、そしてそれに触れると取り返しのつかないことが起きるとささやかれていました。しかしトシオはその話を信じず、ただ森の奥に広がる未知の世界に惹かれていました。
しばらく森を歩いていると、トシオは他の木々とは少し違う、まるで絵から飛び出してきたような美しい桜の木を見つけました。陽の光を受けて、薄紅色の花びらがきらめくように舞っています。その時、トシオはこの木が噂に聞く「呪いの木」だとは思いも寄りませんでした。彼は心惹かれるままに、そっと手を伸ばし桜の幹に触れてしまったのです。
その瞬間、トシオの心の中に重苦しい影が忍び込んできました。それは何か悪意を含んだ不吉なものでした。帰宅後、トシオはその奇妙な感覚を忘れようとしましたが、夜になると恐ろしい夢を見るようになりました。夢の中では森が燃え、村人たちが悲鳴を上げていました。そしてその原因が、自分自身であることに気がつくのです。
村では、突然原因不明の病が流行り始め、人々は次々に倒れていきました。トシオもまた高熱にうなされ、寝込むようになりました。村の人々は不安に苛まれ、誰一人として原因が分からないまま、村全体に暗い影が差し込んでいくのでした。
ある日、トシオは枕元に奇妙なネズミがいるのを見つけました。そのネズミの目はまるで人間のようで、静かに彼を見つめていました。ネズミはまるで話せるかのように、小さな声で語りかけてきます。「トシオ、お前は呪われている。桜の木の下に眠るものの復讐を引き起こしたのだ。」
トシオは恐ろしくなり、ネズミに尋ねました。「どうしてそんなことが起きたの?」
ネズミは言いました。「むかし、この村を治めていた悪い領主がいて、彼は多くの人々を苦しめ、その命を奪った。村人たちの怨念が桜の木に宿り、呪いの力になったのだ。そして何れかの年に、その呪いを呼び覚ます者が現れるだろうと言われていた。それが、今なのだ。」
トシオは泣きながら、「僕はどうすればいいの?」と訴えました。
ネズミはしばし沈黙し、静かに答えました。「お前の命を贄として、桜の木に戻ることしかない。そうすることで呪いは封じられるだろう。」
トシオは村をこのまま苦しませることなどできないと決心しました。そして翌日、彼はふらふらと森へ向かい、再び桜の木の前に立ちました。そこに立つと、まるで自分の身体が木に吸い寄せられるかのように感じました。そして、彼の体はやがて見えなくなり、彼の存在は森に溶け込んでいきました。
不思議なことに、それから病は少しずつ消え去り、村は平穏を取り戻しました。人々は再び桜の木に近づいてはいけないと悟り、誰もそれについて口にすることはありませんでした。
そして、時が過ぎてもその森の中心に立つ桜の木は、トシオという少年がいたことを静かに語っていました。その満開の花びらは、どこか悲しい色をしているように見えましたが、誰もそれを確かめる術はありませんでした。
ただ、夜になると不思議なことに、森を通りかかった者は皆、誰もいないはずの場所から、小さな声で語るような囁きを聞いたと言います。それは、子どもの微かな笑い声のようでもあり、遠い昔の呪いの囁きのようでもあるのでした。人々はただ、そうした囁きが森の外に出てくることがないことを、ただ祈るばかりでした。
その呪いの森は、一見優しい桜の花に覆われ、人々の記憶の中で息づく恐怖の伝承として、今もなお語り継がれているのです。村の子どもたちは、桜の木を見て不思議そうに目を瞠ることはあっても、決してそこに近寄る者はいませんでした。
桜は咲き続け、季節ごとに美しさを振りまきますが、その魅力の裏に隠された悲しみは、誰の目にも見えないままです。ただ、一人だけの少年の記憶が、風に乗って静かに木々の間をさまよっているのです。