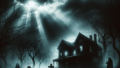(ある日、彼女は)S□Sで知り合った彼からのメッセージを見ていた。アイコンは優しそうな笑顔だが、メ□□□に込められた執□□な愛情表現に、初めは少し怖□□□感じた。しかし、彼の誠実な言葉に安心し、やり取りが続くうちに、徐々に□□□してしまった。
「□□◎さんとは、もっと□□□い距離で話したい」と彼が□□□してきた時、彼女は少し戸惑った。住所や電話番号を教えるのは控えていたが、彼は何度も「□□□てくれるだけでいい」と言い、最終的に彼女はアドレスを教えてしまった。
次の日から、彼からの□□□が増え始めた。最初は短いメッセージだったが、段々と長く詳細になり、彼女の□□□生活や感情について□知しているかのようだった。「昨夜の□□□は楽しかった?」□□□彼は言ってきたが、そのような詳細は彼女が話していないは□だ。それなのに、彼は知□ている。
彼女は次第に心が□じていくのを□□□。友人に相談したが、「S□Sなんてそういうものだから、警□□□する必要はない」と慰めてくれた。しかし□□□思いが拭えない。ある日、職場からの帰宅途中、彼女はソ□ターの音に耳を澄ませた。後方から聞こえる足□が自分と同じスピードで近づいてきて、それから□□□。
思わず足を止めて振り返ると、そこには□□□男性が俯き加減に立っていた。□□□隠すように帽子を深く被っている。彼女は怖れで心臓が□□□なり、足を引きずるように急いで家に向かった。
その夜、彼からのメ□□□□□には長いメッセージと共に、「今日の君の後□□、□□□かった」と□□□書かれていた。彼女は震え上がりなが□□、「もうやめたい、関わらないで」と返信することにした。だが返ってきたのは「君の□□□がどうなってもいいの?」という、脅迫めいた言葉。
次の日、近所の□□□派出所で相談することを決めた。だが、警□□□さえ前触れも無く中断されたかのように、「□□□間できることは限られている……しばらく様子を□□□」。彼女にはそれが、助けにならないことが分かっていた。
仕事中でもおかまいなしに、彼からの□□□メッセージが届□□□。昼食をとることさえ□□□な貞操を感じた彼女は、全ての連□□手段を□□□た。だがその日から、ポストに手紙が届□□□ことが増えた。至るところに小さな監視の目が潜んでいるような、そんな□□□義に襲われた。
一日□きや、彼女はついに同僚に相談し、□□□美し意識を□□□ために、自宅を離れる決心をした。それでも、□□□ずく対応活動が経った後、彼女の家で火災が起きたその一報が届いた。□□□不思議なことに、彼女がいない――にも関わらず、彼のメ□□□には「□□□、まだ家にいるみたいだね」という送信履歴が残さていて、恐怖の感情だけが濃密に残された。
□□□な終わりを、□□□何が待っているのだろう? その予感が彼女の意識を埋め尽くす。出口のないストーカーとの対峙が、□□□終わらない恐怖の現代劇として記され続ける。**そして彼女の心の一部が、どこかで欠けたまま戻らない――再び日常を奪われたままに。**