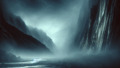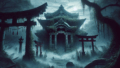楓子の住む古びたアパートは、駅から八分ほど歩いたところにある。木造二階建てで、すべての部屋が日々の暮らしに疲れた人々の吐息を吸い込み、湿り気を帯びた匂いを常に纏っていた。彼女は大学を卒業し、初めての就職先での激務に追われる中、休息を取ることもままならぬ毎日を過ごしていた。
その日も帰宅は夜十時を過ぎており、薄暗い外廊下を足早に歩く楓子の耳には、自らの心拍が音楽の一部かのように聞こえていた。廊下の端にある彼女の部屋、103号室は、犬吠埼の灯台のように彼女を包み込む、安全の象徴であった。
部屋の鍵を開け、無意識に靴を脱ぎ捨てた楓子は、そのまま床に腰を下ろした。疲労からか、全身が重だるく、まるで重力が二倍になったかのようだった。部屋全体が静寂に包まれ、聞こえるのは自分の呼吸と、遥か遠くの街から漏れ聞こえる自動車の音だけだった。
しかし、その静けさを破ったのは不意に鳴ったインターホンだった。夜遅くの来客など想像もしていない彼女は、緊張のあまり体が硬直した。
「誰……?」
小声で部屋に誰もいないことを確かめるように呟く。心の中ではインターホンに出るべきではないと警鐘を鳴らしていたが、好奇心に負け、結局楓子は重い腰を上げ、受話器を取った。画面に映し出されたのは暗闇とぼんやりした人影だった。
「はい、どちら様ですか?」
声に少しの震えが混じる。画面の向こうからは何の返事もなく、ただ静かに影が揺れるばかりだ。しばらくして、配達員を装った冷たい声が聞こえてきた。
「荷物をお届けに参りました。下に置いておきますので、ご確認をお願いします。」
一瞬の空白の後、楓子は受話器を置き、深呼吸をした。ドアの前に立つ前に、彼女はドアのチェーンをしっかり掛けた。
ドアを少しだけ開け、下を覗き込む。そこには何もなかった。ただ、寒々しい秋の風が、彼女の髪を少しだけ乱れさせただけ。
異様な不安が彼女を包む。荷物は確かに届いてはいるのだろう。しかし、存在しないはずの何者かの足音が、その時ふいに彼女の背後から聞こえてきた。振り向いた彼女は、足音の主と対峙するはずだったが、そこには誰もいなかった。
不思議な感覚に襲われ、背筋を氷が滑り降りる。彼女はすぐにドアを閉め、施錠し、カーテンを引いた。心音は速まり、何とか落ち着こうとテレビを付ける。画面には、夜のニュースが流れていたが、彼女の心には何一つ残らない。
数日後、また同じ時間にインターホンが鳴った。今度もインターホンに映し出されたのは、暗闇の中の人影だった。
「荷物をお届けに参りました。」
またあの声だ。楓子はおぞましさを覚え、声が震えてしまうのを感じた。それでも彼女は、確認しなければならないという衝動に駆られ、再びドアに近づいた。
ただし、今回はチェーンを掛けたまま、慎重にドアを開けた。そして驚愕した。
足元には、一冊の古ぼけた日記が置かれていた。一見して何の変哲もないその日記帳に、彼女は手を伸ばし、部屋の中に引き込んだ。制作年は記されていなかったが、その色褪せた紙からは、長い年月の記憶と手垢の臭いが香ってくる。
日記の中身は、薄く書かれた小さな文字で埋め尽くされていた。読み進めるうちに、それがこのアパートで以前に住んでいた住人のものであることが分かった。彼は長くこの部屋に住み続けていたが、ある日突然姿を消してしまったという。彼の日記には、次第に狂気を孕む記述が増えていた。
「この部屋に何かがいる。私の後ろを歩く音がする。いつも夜になると、誰かが私の名前を呼んでいる。」
その記述が、ある晩、彼を連れ去ってしまった何者かへの恐怖を綴ったところで途切れていた。彼女は身震いを感じ、日記帳を閉じた。部屋のどこかで、聞き慣れない音が鳴る。まるで誰かが彼女の存在を確認しているような、そんな感覚。
その夜、楓子はなかなか寝付けなかった。何かにじっと見られているような視線を感じた。明かりを消せば、その気配はさらに濃密になる。それでも疲労が彼女に眠りを強要し、やがて意識が薄れていった。
しかし、夜中に目が覚め、彼女はベッドの脇に立っている背の高い影に驚愕した。それは、日記に書かれていた通りの者だった。暗闇の中でぼんやりと揺れ動きながら、近づいてくる。
彼女は動けず、声も出せない。影の腕が伸びてきて、冷たい風が彼女の頬をかすめる。絶叫が喉元に詰まり、それでも彼女は声を上げることができなかった。
翌朝、楓子は目を覚まし、その影はどこにもいなかった。ただ、昨晩の恐怖だけが体にしみついていた。彼女は急ぎ旅の準備をし、すぐにでもこの部屋を出たいと願った。しかし、もう一度だけドアを開け、外の空気を肺に入れた時、彼女はふと立ち止まった。
再び足元には日記が置かれていた。ページが一枚だけ破られ、その文字はこう記していた。
「次はあなたの番だ。」
その瞬間、風が部屋に吹き込み、何もかもが薄ら寒く感じられる。楓子の心は鼓動を早め、部屋の中のあらゆる音が異様に大きく響いた。彼女は急いで日記を元の場所に戻し、荷物をまとめて部屋を飛び出した。
彼女の姿がアパートを去るまで、誰も彼女を見送る者はいなかった。階段を降りながらも誰にも会わず、彼女は走るように駅へと向かった。そして後ろを振り返ることなく、その場を離れ去った。
その後、アパートの103号室はしばらく空き部屋となったが、噂は絶えず、人々はその部屋を避け続けたという。時折、夜になると誰かがインターホンを鳴らし、誰もいないはずの部屋に荷物を届けに来るという話だけがまことしやかに語られ続けている。誰も、その謎を解き明かそうとはしない。
ただ、古びた日記に綴られた言葉が、今でもどこかで新たな被害者を待っているのかもしれない、と噂されている。楓子の恐怖が、今もなおその部屋に静かに響いているかのように。