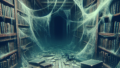聞いた話なのだが、ある友人の知人が不思議な体験をしたという。信じるかどうかはあなた次第だが、少なくともぼんやり胸の奥に黒い影のような不安を残す話だ。舞台は、今からそう遠くない、都会の片隅に位置する古びたアパートだった。
そのアパートは昭和の終わり頃に建てられたらしいが、年月を経たせいか、今では壁にヒビが入り、窓ガラスもガタついて不穏な風の音を奏でていた。外からは何の変哲もない、ありふれた住宅街にあって、ただ一つ、夜になるとぽつりと灯る明かりが印象的だったという。昼間は住人たちが買い物や仕事に出かけており、訪れるのは配達員と新聞の勧誘ぐらいで、住人同士の交流はほとんどなかった。
その知人というのは、名前をAとしよう。Aは仕事の都合で、そこに引っ越してきた一人暮らしの若いサラリーマンだった。新しい生活には期待も不安もあったが、Aはそれなりに新しい環境に馴染んでいった。ところが、引っ越してから3ヶ月が経ったころ、異変は少しずつAの周りで起こり始めた。
最初の異変は薄暗い廊下での独り言だった。Aはある夜、帰宅の途中で薄暗い廊下を歩いていた。そのとき、小さな子供の囁く声が聞こえた気がした。声は確かに「帰ってくる」と言った。振り返っても誰もおらず、ただ廊下の電灯が幽かに揺れているだけだった。最初は疲れて幻聴でも聞いたのだろうと思い、その場をやり過ごした。
しかし、その夜からAは一つの夢を見るようになった。夢の中で、彼は薄暗い廊下を歩いている。先には古びた木製のドアがあって、そのドアは彼がもう何度も見るうちに自然と覚えた、散歩のルートの一部にあったものだ。ドアの向こうには決まって長い廊下と、無数の影の中に佇む小さな子供がいた。その子供は彼に向かって何か言いたげに手を振っていた。しかし、その顔はどこかぼんやりとした輪郭を持ち、見事に記憶の網から逃れた。
夢が続く中で、Aは朝になるといつも汗をかいて目が覚めた。目が覚めたときには、何もないはずの天井に影がゆらゆらと揺れている気がして、彼はしばらくそれを見つめることしかできなかった。彼はそれがただの悪夢だと思い、自分を落ち着かせようと試みた。
ある晩、Aはまたもや廊下でその囁き声を聞くこととなった。今回は前よりもはっきりと聞こえた。「早く見つけて」。その声には不思議な哀愁と、何かを求める切実さが感じられたという。しかし、やはり振り返ってみても、そこには誰も存在しなかった。
Aはさすがに不安になり、ある土曜日の昼間、その古びたドアまで足を運ぶことにした。太陽の光が差し込む明朗な昼下がり、アパートの建物は静けさに包まれ、新しさと古さが混在する空間に孤独に浸されているようだった。ドアに近づくと、鍵が掛かっていることに気付きつつも何かに手招きされている気がして、戸惑いながらもノックをした。
当然のことながら、応答はなかった。Aはふと、ドアの下に何かが落ちているのを見つけた。それは小さな銀色の飾りで、何やら古い紋章が刻まれている不思議なものであった。Aはその飾りを手に取った瞬間、肌に電流のようなものが走ったのを感じた。
その日の夜、寝るときに彼はその飾りを机の上に置いておいたが、またもや夢の中でその子供に出会うことになった。今度、その子供は以前よりもはっきりとした姿を見せ、彼に向かってこう告げたのだ。「見つけてくれてありがとう。でも、まだここにいるの」。その言葉と共に冷たい風が夢の中を駆け抜け、Aは目を覚ましたとき、心臓が激しく鼓動を打っているのを感じた。
翌朝、Aはこの不可思議な出来事を誰に話しても信じてもらえないだろうと考え、自分の記憶を改めて紡いでみることにした。しかし、どうしてもその夢の中の子供の顔や状況が曖昧にしか思い出せない。そんなもどかしさの中で、彼はさらに自分の感じている事柄が現実のものなのか、ただの幻想なのか分からなくなっていった。
彼はその晩から、夜更けにその廊下を通るたびに不思議な感覚に包まれることになった。囁き声、夢の中の子供、そして手元にある小さな銀色の飾り。これらのつながりを何とか理解しようと試みたが、Aの中でその疑問は解決の兆しを見せず、未だ霧の中にあるかのように感じられていた。ある意味では、その謎は彼の生活の一部となり、不思議な形で彼を捉えて離さなかったのである。
この体験がAにとっての終わりなのか、それとも新たな始まりなのかは、誰も知らない。彼は今もそのアパートで暮らしているという噂もあるが、あくまで噂話に過ぎない。知人の友達が経験したというこの話は、きっと現実かどうかよりも、その曖昧な存在感が我々の眠る夜に忍び寄り、そっと心を揺さぶるのだろう。だからこんな話は、いつの時も語り継がれるに違いない。