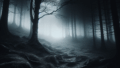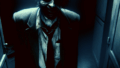私の故郷は、田舎の小さな町だ。山々に囲まれ、古くからの風習や言い伝えが色濃く残る場所である。私は子供の頃からこの町の人々と同じように、祖父母から妖怪や幽霊の話をたくさん聞いて育った。信じがたいものもあれば、ぞっとするものもあったが、不思議なことにどの話も現実味を帯びていて、背筋に冷たいものが走ることがよくあった。
私がもう二度と思い出したくない恐ろしい体験をしたのは、中学生の頃だった。その年、町の南にある山の麓に、祖父母と共に暮らしていた。祖父は山で木こりをしており、森林の管理や木材の供給を生業としていた。私は、祖父の仕事を手伝うことがよくあり、その日も朝早くから山に出かけ、祖父の傍で斧を振るっていた。
その日は特に暑く、湿気が重くのしかかるようだった。昼を過ぎると、私たちは少し休むことにし、切り倒した木の根元に腰を下ろした。祖父は、ふと遠くを見つめながら、ぽつりと語りだした。
「この山にはな、昔から“つくも神”がいると言われてる。古くて使われなくなった道具や器具に宿る霊だ。お前、この山では古いものを粗末にしてはいかんぞ。」
祖父の話を聞きながら、私は特に気に留めることもなく、ただ流れていく濡れ落ち葉を眺めていた。そのとき、ふと背後の暗い林から、不気味な視線を感じた。何かがこちらをじっと見ている気がして振り向くと、そこには何もなかった。ただ風が木々を揺らし、葉の擦れる音だけが耳に届いた。
その夜、私は布団に入ってもなんだか眠れなかった。祖父から聞いた“つくも神”の話と、あの視線の正体が気になってしかたなかった。一時間が過ぎても眠れず、私は喉の渇きを感じて台所へ向かうことにした。階段を下り、廊下を歩くと、居間にある古い置物の馬が目に入った。その瞬間、私は背後に人の気配を感じた。それもただの気配ではない、確かに何かが私を見ていると分かった。
恐る恐る振り向くと、そこには確かに“何か”がいた。ぼんやりとした人形のような姿。その目は燃えるように赤く、口元には薄笑いを浮かべていた。私は恐怖で声も出せず、その場に立ち尽くしてしまった。何も考えられず、ただその“何か”と目が合っていた。
どれくらいの時間が経ったのか分からない。気付けば、ふと視線を感じなくなって、私はその場にがくりと膝をついた。しばらく動けぬまま、やがて恐る恐る居間を離れ、部屋に戻った。その夜は結局、ほとんど眠れなかった。
翌朝、私は祖父に昨夜のことを話した。祖父は黙って私の話を聞いていたが、やがて深くため息をつき、私にこう言った。
「つくも神に目をつけられると厄介だぞ。古い物には魂が宿る。お前が見たのは、その警告かもしれんな。」
そう言う祖父は、どこか遠い目をして言葉を継いだ。「今夜、供養をしよう。魂を鎮めるにはそれが一番だ。」
その夜、祖父とともに山の麓へ行き、古びた道具や壊れた器具を用意した。祖父はそれらを慎重に並べ、酒と米を供え、静かにお経を唱え始めた。私も祖父の隣で手を合わせ、心の中で「お願いだから、もう何もしないでくれ」と祈っていた。
翌日、その“何か”は姿を見せなかった。だが、あの視線の冷たさは今でも忘れられない。あれは本当に“つくも神”だったのか。それとも、私が何か見てはいけないものを見てしまったのか。
その後も自然豊かな故郷で暮らしているが、夜になると時折、あの時の視線を思い出すことがある。私が体験したのは、果たして偶然の産物だったのか、それとも長きにわたるこの土地の伝承が警告を発したのか。何にせよ、またあの目に会うことは二度とないよう、祈るばかりである。
これが、私が過去に体験した幽玄な恐怖だ。今でもこの話を思い返すと、背筋が凍るような感覚を覚えてしまう。もしかしたら、こういうものの存在を否定することはできないのかもしれないが、感じたくないものは確かにあるのだ。おかしな話だが、この町の古伝承や文化を尊ぶ心が、初めて少しは分かってきた気がした。そんな体験だった。