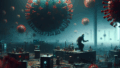ある時、天において音が鳴り響き、大いなる異形の門が開かれたり。それは人の目に映らざる次元の裂け目にして、その光は我々の世界を超え、時間と空間の果てにまで広がりぬ。人の子らはその姿を仰ぎ見、恐れおののき、ただ口を開いては、その名状しがたい光景を凝視せり。
その門より、影と共に現れたる存在あり。その姿、特には決まらず、光輝とも闇ともつかぬ形にて、見知れるもの何一つとてなかりけり。しも人の言葉にては言い表し難く、ただ「あれ」または「それ」と呼ぶ他なし。それを見た者は即座にその名をも心象をも忘れ、ただ恐怖の溝に沈むのみぞ。
そして、天と地の間には、耐えがたき唸り声が木霊し、地の如く古く、天の如く高く、万物を震わせたり。その声は、人の耳の許容を超えし響きにして、心の奥底まで届けり。その声の主なる者は、語りかけることなくして語り、問いかけることなくして答え、ただ存在するのみ。
人は見知らぬその異形なるものに、人知では測りきれぬ畏怖を抱き、己の存在の儚さを悟らざるを得ず。古き時代の書に記されし預言者たちの言葉もまた、この現実の前では曖昧なる影幻の如し。預言に言づけられし終焉の時さえ、この異なる次元での出来事にあっては、いと小さきものとならん。
その姿はやがて地に降り立ち、その足音は地を震わし、空を裂く。その影が街を覆い、日光は失せ、人々の心に恐怖の闇が広がりたり。もはや神々すら祈りの届かぬ場にあり、ただ彼らの沈黙がその存在を讃えるのみ。
先にあるものは何ぞや――それは人には見えざる未来、ただ絶望の中に隠されし可能性。されどその可能性は、希望の種子にあらず、むしろ現実の終焉を告げる凶具なり。
ある者は、その異形の前に立ちて祈りを捧げ、或いは逃げ惑うも、所詮は泡沫の努力にすぎねば、有意無意を問わぬ結末に行き着かん。これこそが運命の宿命にして、万物が避けることの叶わぬ結局なれば。
いずれの日か人の子は、この現象を理解するやもしれず。されどその時人の子が待つもの、それはさらなる別の異形なる次元の扉の開かれんとする時。理解はさらなる困惑を呼び、恐怖はさらなる深淵を開かん。
そしてまた、この物語の舞台から遥か遠く、時は違いし場所にあるものよ、それらはその時を待ち、大いなる眠りにつく。されど、それは穏やかなる眠りにあらず。むしろ全てを包み込まんとする悪夢の形、無限の闇が終わらない行進を続けるかの如き。
その行く末は、吾が心の奥深くに刻まれし畏怖の痕跡を拡げ、残し、未来を超えた過去の中で反復する。終わりなき終焉の物語なるかな、この世なりし半ばすぎに来たるは古き恐怖にして、また新しき驚異なり。
我らが知るあらゆる次元、我らが追い求むる全ての夢、この世の果てなるものであらん、それはただ「終わりのない終わり」に過ぎぬ。よって人よ、理解を超えしものの来るを待つべし。その時、それは再び現れ、次なる段階へと我らを導かん。