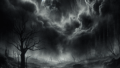私は、かつて大学時代の友人たちと一緒に日本のとある山奥にある神社を訪れたことがある。その神社は「触れてはならない聖域」として地元では有名だった。無論、噂話として興味が湧いた私たちは、夏休みの冒険としてその神社を探検することにした。
神社は地図にすら詳しく載っていない。山道を進み、地元の人々に道を尋ねながら、ようやく辿り着いた。森を抜けると、そこには杉の木立に囲まれた古びた鳥居が現れた。彼方此方に苔が生え、どこか異様な雰囲気を醸し出していた。鳥居のすぐ内側には朽ちかけた案内板があり、かろうじて読める文字で「立入禁止」と書かれていた。しかし、我々は好奇心に駆られ、その警告を無視して奥へと進んで行った。
神社の境内は不気味なほど静まり返っていた。参道の両側には朽ちた石灯籠が並び、誰かの気配が全く感じられなかった。その東京の喧騒とはまるで別世界、異界に足を踏み入れてしまったかのような感覚が、私の背筋を冷たくさせた。
友人たちと私は本殿に辿り着くと、自然と声を潜めるようになった。木造の建物は古く、軋みの音が風に紛れて聞こえてくる。私はふと、本殿脇にある賽銭箱の前で立ち止まった。「なんだか失礼なことしてる気がするなぁ」と、友人の一人が言ったが、誰もそれに返事をせず、ただその場を去ろうとした。
しかし、そこで不思議なことが起こった。突然、境内の空気が変化したのだ。まるで何かが私たちを見ているような感覚。背後からゾクゾクとした寒気が走り、振り返ってみると、木立の間に人形のような何かが立っているのが見えた。
我々は慌てて本殿を離れ、一目散に来た道を引き返した。しかし途中で、私は奇妙な錯覚に囚われた。先ほどまでにぎやかな友人たちの笑い声が、いつの間にか沈黙に変わっていた。慌てて周囲を見渡すと、一緒にいたはずの友人たちの姿がすっかり消えていた。
「皆、どこだ!」私は声を張り上げたが、返答はない。ただ静かに森のざわめきが響くだけだった。半ばパニックになった私は、正しい方向が分からぬままに走った。やがて体力の限界が来て、足が動かなくなったところで膝を突いた。
その時、遠くから鈴の音が聞こえてきた。シャラリ、シャラリと、規則正しい音が近づいてくる。恐怖のあまり私は必死に目を閉じて音の主を確かめないようにした。だが、音が止んだ瞬間、気になって目を開けてしまった。
そこには、白装束を纏った古めかしい神職の姿をした男が立っていた。顔は朧気で判然としないが、冷たい視線だけはしっかりと私を捉えている。彼は無言のまま手にした鈴を鳴らし続け、その節々で私は感覚を失いそうになった。
「帰れ」と、その不思議な存在は心の中に直接語りかけてきたようだった。私は意識の彼方で必死に「はい」と応じたように思う。その直後、気付けば森の入り口に倒れ込んでいた。
地元の警察が私を見つけた時、私は意識を取り戻しつつあり、すぐに友人たちの安否を尋ねた。幸いにも、彼らも助け出され、全員無事だったことを知り安堵した。しかし、この出来事は私たち全員に深い影を落とした。何よりも、あの神社に二度と近づかないことを心底誓った。
この体験を話そうとすると、いまだに背後に冷ややかな視線を感じることがある。あの場所は実在するが、何かを侵さねばならない理由などどこにもない。あの時、私たちが遭遇したものが何であったか、そして何故そんなものが現れたのか、知る由もない。ただ、その森はいまだに聖なる領域として静かに息づいている。きっと、これからもそうあるべきなのだろうと、今は信じている。