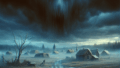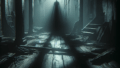山奥にひっそりと佇む古びた木造の宿があった。どこか忘れられたような場所で、滅多に人を寄せ付けないこの宿は、地元の者が言うには百年以上も前から存在しているという。道なき道を進んだ先に、その建物は静かに存在感を放っている。かつては賑わっていた時代もあったのだろうが、今ではその面影を残したまま、風雨にさらされて朽ちるに任せているかのようだった。
ある夏の夜、東京から来た若者たちがその宿に宿泊することになった。都市の喧騒を離れ、彼らは自然の中で休息を求めるためにこの地を訪れたのだ。メンバーは五人、大学の同期で、各々がそれぞれの事情を抱えながらも、こうして旅行を共にする間柄だった。
宿の管理人は、一見して年老いた女性で、彼女が迎え入れるや否や、若者たちはどこか薄暗い印象を受けた。彼女は無言のまま鍵を手渡し、「食事は七時。夜は絶対に一階へ降りないように」と言い残して去った。その声には何か込められたものが感じられたが、彼らの思考の中では深く掘り下げられることなく、軽く流されてしまった。
過ごしてみれば、意外にも部屋は快適だった。いささか古びた畳の匂いと、どこか懐かしさを感じさせる家具の配置。窓から差し込む月の光は、壁に奥行きを持たせるように影を落としている。
夜が深まるにつれ、彼らの体にじんわりと不穏な空気が漂い始めた。それは明確な理由のない不安感であり、感覚的なものに過ぎないと思われたが、誰も言葉に出すことができなかった。やがて、不意に床下から響く音が、彼らの耳を捉えた。鈍い音と、何かがこすれるような音。好奇心と恐怖の狭間で、彼らは何もすることができずに耳を澄ませた。
「おい、どうする?見に行くか?」勇気を奮い起こして一人が口を開いた。薄光に照らされたその顔は、普段の頼もしさを欠いていたが、それでも仲間たちはその一言に勇気づけられた。
「下に行くのは止めようって言ってたけど、気になるよね」誰かが答えた。
彼らは静かに階段を下りた。手にした懐中電灯の光が揺れ動き、古い木材が軋む音が響く。二階廊下の寂しい長さを置き去りにして、彼らは一階のフロアにたどり着いた。その場所はさらに暗く、僅かに漂うかび臭さが彼らを迎えた。
音の正体を確かめようと、彼らはついにその音の元へと近づいた。古びたドアの前で立ち止まり、彼らは顔を見合わせた。一人が手を伸ばしてドアに触れた瞬間、音は急にやんだ。緊張が走る。
ドアをゆっくりと開け放った時、真っ暗な地下へと続く階段が彼らを迎えた。懐中電灯の光が石壁を照らし、冷たい空気が肌に触る。ためらいを振り払い、彼らは階段を下りた。
地下室にたどり着くと、彼らの目に飛び込んできたのは、畳まれたままの古い布団と、辺り一面に置かれた背の低いテーブルだった。不可解なことに、それらは今しも誰かがここで生活しているかのように整っていた。
「何だ、ここ…?」誰かが呟いたと同時に、再び音が聞こえてきた。今度はもっと明確に、すぐ近くから。彼らは音の方へと目を向けた。
それは壁の奥からだった。心の中で、彼らは何か震えるような恐怖を感じながらも、止めることができなかった。恐る恐る近づいてみると、細い隙間からほのかに光が漏れていた。誰かがそれに手をかけた瞬間、棚ごと壁が動き、そこにもう一つの部屋が浮かび上がった。
中には古い祭壇があり、その中央には異様な姿をした仏像が鎮座していた。それを見た瞬間、五人の皆が無言で後ずさりした。何か言葉を失わせるほどの力がその像には宿っていた。
「もうここを出よう」と、誰かが口にした。しかし、その言葉が発せられると同時に、不気味な霧が部屋一面に立ち込めた。彼らは慌てて元の地下室へと引き返そうとしたが、階段の向こうから現れた人影が行く手を阻み、彼らを沈黙させたのだった。
静かな笑みを浮かべた管理人の女性だった。彼女はそのまま彼らを見つめている。目にはどこか狂気じみた輝きがあり、彼らはその場から動けなくなってしまった。
「ここで過ごすのが運命だったのですよ」と彼女が言った。その響きは深い洞窟に反響するように、彼らの心に突き刺さった。逃げ場がないと悟った時、彼らはどこからか誰かの囁き声が聞こえるのを感じた。
「あなたたちの居場所はここよ」
そんな声に振り払われ、彼らは何とか声を上げながらその場から逃げ出した。階段を駆け上がり、うねるような戸口を潜り抜け、彼らは宿を飛び出した。しかし、その後ろからなおも聞こえる低い笑い声が追いかけてくるようで、その恐怖から彼らは夜明けまで逃げ続けた。
翌日、恐る恐る戻った彼らだが、あの宿が何事もなかったかのように静まり返っているのを見て、何か悪夢でもみていたのではないかと錯覚した。しかし、一つだけ確かなのは、あの地下室で感じた恐ろしい感覚と、あの笑顔の記憶が彼らに染み付いて離れないということだった。
それ以後、彼らは二度とその宿を訪れることはなかった。そして、何年も語り合うことなく過ごした後、それぞれが次第に思い出を霞ませていき、都市に戻り生活を続けた。ただ、稀に夜が深くなると、あの時の囁きが蘇り、不愉快な安眠を妨げることがあるという。それは深い記憶の中で囁き続け、彼らを思い起こさせるのだ──その宿に忘れ去られた運命が幾世、幾代に渡り続くことを。