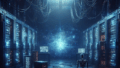私はある地方の古びた村に住んでいた。その村では、長い間「オオサマの祠」と呼ばれる場所が禁忌として語り継がれていた。村の人々はそこには近づかず、子供たちには決して足を踏み入れないようにと言い聞かされていた。
ある晩、私は仲間たちと一緒に酒を飲みながらふざけていた。そして話題は次第に、「オオサマの祠」の禁忌に移っていった。皆、その場所について根拠のない噂話を面白半分に語り合ったが、私はなぜかその話に強く惹かれてしまった。
ふとした好奇心から、「一度だけ行ってみるのもいいじゃないか」と仲間たちをそそのかしてしまった。私たちは酔った勢いもあって、そのまま祠へと向かうことに決めた。夜の森は異様に静かで、月明かりがかすかに私たちの道を照らしていた。
祠にたどり着いた時、私たちはその場の不気味な雰囲気に一瞬言葉を失った。祠は古びた石で作られ、苔むした様子をしていた。中に入ると、古い祭壇と神体が朽ち果てた状態で放置されていた。誰かがふざけて供物のようなものを触ると、途端に冷たい風が吹き抜け、ろうそくの火を揺らした。その時、私は奇妙な感覚に襲われた。背後に誰かが立っているような気配を感じ、冷や汗が背筋を伝った。
その夜は何事もなく過ぎ、私たちは何事もなかったかのように村に戻った。しかし、その日を境に私の周りで奇妙なことが起こり始めた。最初に気付いたのは、夜になると家の周りで不気味な音が聞こえることだった。風の音に混じって、何かが地面を這うような音が絶え間なく続いた。
さらに、仲間のひとりが突然高熱を出し、医者も原因がわからないと首をかしげるばかりだった。彼はうわ言のように「オオサマを怒らせた」と繰り返していたが、誰もその意味を理解できなかった。
数日後、別の仲間が道路で奇妙な事故に遭った。彼の車のタイヤが突然パンクし、制御を失ったという。本人はかすり傷ひとつなかったが、彼もまた、「祟りじゃないか」と不安を口にしていた。
私自身にも異変は及んできた。ある夜、自室で眠れずにいると、壁に黒い影のようなものが見えた。心臓が凍りつくような恐怖に襲われ、動けなくなった私をその影はじっと見つめていた。その目は存在しないはずのもので、この世のものとは思えない冷たさを湛えていた。
次の日、村の古老に相談に行った。彼は話を聞き終えると困惑の表情をしながら言った。「あの『オオサマの祠』には手を出してはいけない。昔、村で大きな事件があった。ある村人たちがその場所を冒涜し、彼らは全員、不運によって死んでいったと。」
その言葉に背筋が凍る思いだった。私たちも同じ運命を辿るのかもしれない、と思い詰めた私はどうすればいいのか分からず途方に暮れた。古老は何かを迷うように私を見つめた後、観念したようにひとつの提案をした。
「かつてその祠を浄める儀式が村にはあった。それを行えば、少しは穏やかになるかもしれん。ただ、不確かな古い言い伝えに過ぎんがな。」
私は一縷の望みを託し、古老の手ほどきを受けることにした。仲間たちにも事情を話し、全員で老いた神主の指示に従いながら、数日後に儀式を決行した。儀式は深夜に行われ、私たちはそれぞれ慎重に言われた通りに動作を行った。
その結果、不思議なことに、次の日から奇妙な現象は少しずつ収まっていった。仲間の一人は快方に向かい、私も夜になると静寂を取り戻せた。だが、心の底には常に何かが囁くような声が消えなかった。「本当にこれで終わったのだろうか」と。
それ以来、私たちがあの祠について話すことはなかったし、あの場所へ足を踏み入れることも決してなかった。しかし、村を離れた後に聞いた話では、再び何かの影が現れるようになったと耳にした。私は、その呪いがいつか再び私たちを追ってくるのではないかという恐怖に怯え続けている。その恐怖がいつまでも消えない限り、私たちは真の意味で解放されることはないと思う。
この体験が私に教えてくれたのは、一度失った者にも再び救いの手を差し伸べることができるとしても、過去の過ちがもたらす負の連鎖を完全に断ち切ることは極めて難しいということだ。そして、それは決して他人事ではなく、いつ何時でも自らを襲う可能性を秘めているのだ。だからこそ、私は慎重に生きることを選び、未来への不確かさに備えることにしている。
私の話は、このまま終わるかもしれない。しかし、今夜も風の音が不気味な叫び声に変わるとき、何かがその向こうで待っているような気がしてならない。この呪いは、まるで忘れられた過去の、心の奥に潜む罪のように、じっとその時を待ち続けているのだ。