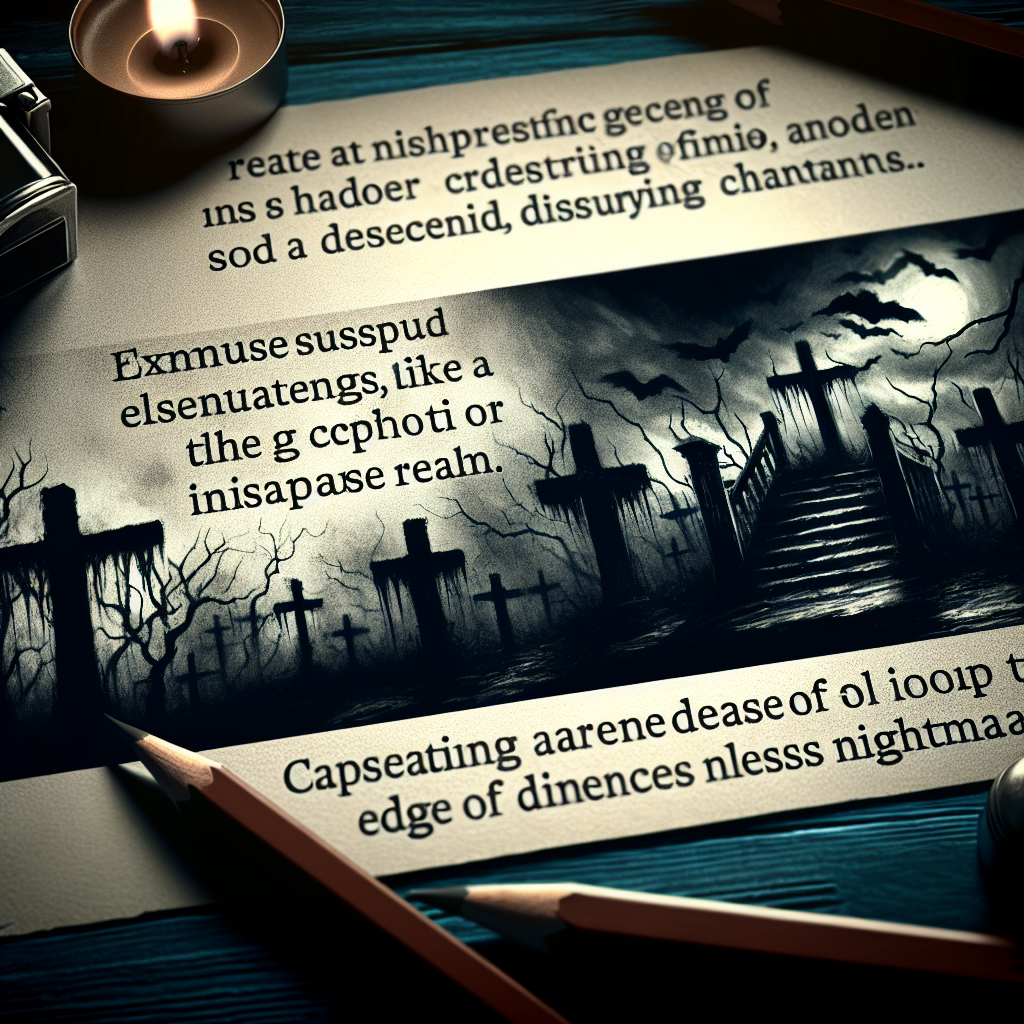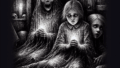その村は、山影にひっそりと横たわっていた。人々の暮らしは月日の流れに逆らうことなく、静かに織られていた。木々のざわめきが語るのは、古くからこの地に根付く伝承。数多の季節を越え、静寂の中で積み重なっていく物語は、時として忘れ去られた神々の名を囁く。しかし村の誰も、その囁きに耳を傾けることはない。なぜなら、それが「触れてはならない聖域」だと、祖先からの教えがあったからだ。
村の端に、一つの古い神社があった。社の周囲は鬱蒼とした森に包まれ、その存在を視界から隠していた。鳥居は苔むし、年月の重みに耐えてかろうじて立っている。神社に続く道はすでにほとんど見えなくなり、藪が生い茂る中に僅かな獣道が残るのみだった。
幼い頃、村の大人たちはことあるごとにその神社に近づいてはならないと子供たちに言いきかせた。そこは「神々の領域」であり、人の手で触れるべきではない場所。もしも禁を破れば、恐ろしいことが起こると。
しかし、恐れは何かを知ることへの欲望を完全に押し止めるものではない。その日、勇気というよりは無謀から、郷田という少年が神社へと足を踏み入れた。彼の心を突き動かしたのは、最早他の誰も信じることのない古の神々への興味だった。友人たちには「探検」として語り、ひとりでこっそりとその「聖域」へと向かった。
鳥居を潜ると、辺りは急にひんやりとした空気に包まれた。それはすぐに消え去り、彼の背後、村の存在を隠すような静寂が戻った。木々の隙間から漏れる陽の光は、どこか重たげで、その中に立ち尽くす郷田を冷ややかに包み込んだ。彼は心中の不安を振り払うように歩を進め、敷石の参道を歩き出した。
やがて石段が現れ、その先端に幽かに見えてくるのは、朽ちかけた拝殿。祠はしばらくの間、郷田の訪れを待っていたかのように、静かに佇んでいた。彼は一歩一歩ゆっくりと上がっていく。石段に残る苔が足裏で鳴き、何かを訴えるようだった。
片手で掌をかざし、薄暗い中でも祠の様子をとっぷりと見つめる。何故か物言わぬ拝殿からは、かつての祀りの賑やかさを感じ取ることができた。祭壇の上には古びた御札が幾枚か、風に吹かれてぱたぱたと音を立てている。郷田はそれをじっと見つめた。すると、どこからか低い唸り声が響いてきた。それは風の音ではない。何か生き物が近くにいるかのような、苛立ちを含んだ唸り。彼はその音に促されるように、境内の奥へと進んだ。
拝殿の裏手には、もう一つの祠があった。想像以上に小さく、煙草箱を少し大きくしたほどの大きさだ。郷田はその前にかしこまり、祓う手を合わせた。すると背後で太い枝が折れる音がした。振り返ると、目の前に立っていたのは老人だった。村の者ではない。村で見たことがあるはずの顔ではなかった。
睨みつけるような目、深い皺で刻まれた顔。衣服は黒ずんでいる。それが何か特別な姿を意味するものなのか、郷田には分からなかった。ただ、視線が合った瞬間、彼は背筋に冷たいものを感じた。「ここは神々の土地だ、去れ…」という低い声が頭の中に直接響いてきた。
恐怖が足をすくませ、身体を動かす力を失わせた。しかしその声は、再び脳裏に響き渡り、今度は強制的に郷田を解放し、その場から駆け出させた。踏み外しそうになる石段を斜めに手をつき、息も絶え絶えに追い出されるように鳥居を抜け出した。
村に帰りつくと、そこにあるべき村の姿はなかった。家々は古めかしく、どこか違う時代を彷彿とさせる。信じられない思いで村中を駆け回ったが、自分の記憶にある光景はどこにも見当たらない。人の姿もなく、不自然な静寂が村を包んでいた。
絶望感に打ちひしがれ、その場にへたりこむと、不意に目に映ったのは地面に突き刺さった一本の枝。その先からは、滴り落ちる血のようなものが流れていた。郷田はそれを掴み取り、手を巻いて柱のように立ち上がると、霧がかかったような目で再び神社の方向を見つめた。
禁忌を犯した報いなのか、彼は決して解けることのない場所へと足を運んでしまったのかもしれない。村と神社、この二つの境界は、彼にとって終わりのない悪夢の始まりであった。決して踏み込んではならない聖域。ただの探究心が齎した恐怖の真実は、知ることのできないもう一つの世界を垣間見てしまったことにある。
郷田はもう一度、深い溜息をつき、その場を立ち去ることができぬまま、薄明かりの中にただ一人、震えるように立ち続けた。この場に現れることを繰り返すその影は、いつの日か彼を迎え入れるのだろう。村に戻れる日が訪れることはないと、彼はようやく悟ったのだった。
それでも彼の心にこびりついて離れないのは、あの老人の目。そして神々の囁き。それは、思い出すたび背中をぐっと押し、彼をこの異なる現実へと引き戻すのだ。終わりのない輪廻。それがこの地の持つ、真の恐怖だった。